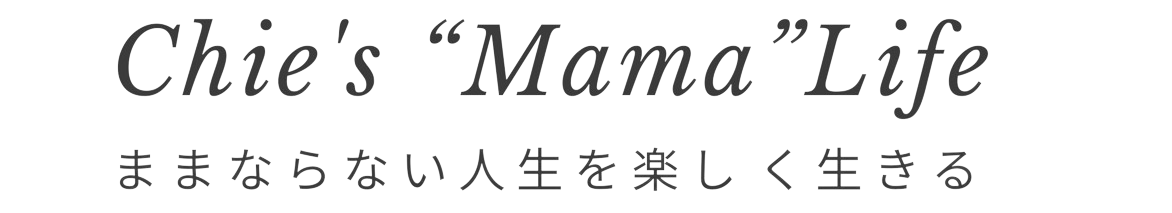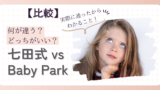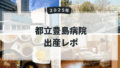我が家の息子は1歳4ヶ月から現在(5歳)まで、七田式教室に通っています。
(1歳4ヶ月以前はベビーパークへ通っていました。ベビーパークと七田式の比較については以下記事を御覧ください!)
来年度の年長クラスも引き続き通室予定ですが、このあたりで一度、七田式についてのレビューをしてみたいと思います!
1.七田式とは
七田式教育の方針
人間が本来持っている能力を最大限に引き出すために、生涯で最も吸収力の高い幼児期からの取り組みを行うのが「七田式教育」。
何よりも「心の教育」を大切にしており、キーワードは「認めて、ほめて、愛して、育てる」。
展開サービス
七田式教室
全国にある200以上のフランチャイズの七田式公認教室に通うことができます。
教室運営は各フランチャイズ先となりますが、使う教材や設定コース(幼児コース、小学生コースなど)は共通しています。
息子が通っているフランチャイズグループでは都内を中心に関東圏、関西圏に23教室を運営しています。その他の大きいフランチャイズグループでは関東・上越エリアを中心に32教室を運営している会社などがあります。
フランチャイズ先は大小様々だと思いますが、グループで複数教室を運営している場合には、レッスンの振替をグループ内の他教室でも取得できるなどの利点があり、一方で、先生の異動などの可能性もあります。
※具体的なレッスン内容は以下「七田式教室のレッスン内容」参照。
幼児/小学生教材の販売
質の高い七田式プリントやフラッシュカード、取り組み教材を公式オンラインショップで購入できます。
そのため、通室や通信教育の受講をしなくても、手軽に家庭で七田式のメソッドを取り入れることが可能です。
通信教育
幼児コース(0歳〜6歳が対象)と胎教コースがあります。
幼児コースでは、年齢にあった教材が送られるので、それを使って家庭で取り組みを行います。
近くに教室がない場合や、送迎が負担になる場合にも七田式教育を取り入れることができます。
フラッシュカードなども保護者が行う必要があるので練習が必要ですが、毎日行うことができれば、高い効果が期待できそう。
2.七田式教室のレッスン内容
子どもの発達・年齢に合わせて、フラッシュカードや歌、取り組みを行います。
年齢ごとのレッスン内容
各教室ごとにレッスン内容は少しずつ異なると思います。以下は息子の通っている教室の例です。
以下いずれの年齢でも、前半にフラッシュカードがあり、後半に取り組みがあります。
フラッシュカードは「かなえちゃんカード」もありますし、多種多様なカード(有名な芸術家・作品の名前、職業、楽器、国旗、等々)があります。
0・1歳
フラッシュカード、絵を見ながら歌を聞く、手先の取り組み(積み木、紐通し用のくまをつまむ、絵合わせカード、ひらがなかるた、曲に合わせて楽器を鳴らす、カップ積み、ベビーコロールで線描き)。
2・3歳
フラッシュカード、絵を見ながら歌を聞く、ひらがなの歌、リンク記憶(お話記憶)、取り組み(ひらがなかるた、20玉そろばん、線描きプリント、めいろ、くまの紐通し、線に沿ってハサミで切る、5色キューブを見本の通りに並べる)。
4・5歳
フラッシュカード、円周率の歌、漢詩・俳句、ペグの歌、リンク記憶(お話記憶)、取り組み(100玉そろばん、タングラム、めいろ、紐通し、ニキーチン積み木模様づくり、時計の時刻読み、お金のおもちゃを使って買い物)。
3.七田式の特徴
①暗唱
いろいろなものを歌にして覚えること&覚えた歌や文章を発表する「暗唱」は七田式教育の特徴の1つです。
覚える内容そのものよりも、幼い時期に「記憶の回路」を作ることが重要です!
また、覚えたものを先生の前で発表するので、人前で発表する良い練習になります。
「テキスト掲載曲24曲」や「円周率100桁」「円周率1〜300桁(通し)」など、カテゴリごとの基準を達成すると、名前・日付入りの記念トロフィーや盾がもらえ、モチベーションになります。
例えば、円周率(3.14…)に音程をつけた「円周率のうた」というものが、100桁ごとに5曲=円周率500桁まで用意されていて、設定された条件を達成すると盾がもらえます。
「1〜100桁」「101〜200桁」「201〜300桁」「301〜400桁」「401〜500桁」という100桁ごと5曲の歌に分かれており、「1〜100桁(=1曲歌う)」「1〜300桁の通し(=3曲続けて歌う)」「1〜500桁の通し(=5曲続けて歌う)」をクリアすると、それぞれ名前・日付入の記念の「盾」がもらえる。
息子が暗唱達成した円周率桁数と年齢
- 円周率1〜100桁:3歳
- 円周率1〜300桁(3曲通し):4歳
- 円周率1〜500桁(5曲通し):5歳
覚え方
暗唱に取り組む際の「覚え方」(覚えさせ方)ですが、「音源のかけ流し」が基本です。
覚えてほしい曲等の音源を食事中などにひたすらリピート再生します。
繰り返しかけ流しておくと、子どもは自然と覚えてしまいます…!
子どもが「覚えた!」と自信を持つと、突然アウトプットとして歌い始めたりするので、親はテキストを見て、子どもが正しく歌えているか(言えているか)チェック!(歌詞テキストの写真を撮っておくとすぐ確認できて便利◎)
円周率100桁くらいならすぐに覚えてしまいます!
なんとなく一日流していただけで円周率100桁を歌い出したときの衝撃は今でも忘れられません…。「子どもの潜在能力ってすごい!!」と鳥肌が立ちました。皆さんにも是非あの経験をしてみていただきたいです!
注意点
音源の発音が明瞭でなかったり、早口で聞き取りづらいと思われる箇所があれば、歌詞を見ながら親が正しい言葉をハッキリと聞かせておくと良いです。
子どもが音源の発音を一旦勘違いして覚えてしまうと、あとからその部分を修正することはかなり困難です。(経験あり)
息子の場合、「円周率301〜400桁」にトライしていた頃、で息子が「4」と「5」を取り違えて覚えてしまった箇所があり、軌道修正するのにかなり苦労しました。
「円周率301〜400桁」だけの暗唱であれば息子も意識が行き届いて正しく歌えるのですが、「円周率1〜500桁の通し」を暗唱発表する際には該当箇所への意識が薄れてしまって何度も間違えてしまう…ということがありました。
②発表会
運営するフランチャイズグループによって開催方法などは異なると思いますが、息子の通っている教室では、運営グループ内の各教室合同で、年に一度、課題曲・詩などを舞台の上で発表する「発表会」があります。(参加は任意)
年齢ごとに課題は異なります。
年齢ごとの発表内容(課題)
- 1・2歳児・年少前クラス:親と一緒に舞台に上がり、歌に合わせて楽器を鳴らしたり、親子で歌を発表。
- 年少〜年長クラス:一人で舞台に上がり、歌や詩の暗唱を発表。
- 小学生クラス:歌や詩の発表のほか、自分が研究したテーマをパワーポイントを使って発表する子もいたり、スタイルは様々。
参加意義
発表が終わると、名前・日付入りの記念メダルが授与されるので、良い思い出・モチベーションになっています。
1歳児〜年少前クラスの年齢から発表会に参加する意味は、「舞台慣れ」と、「上の年齢の子が行う発表から刺激を受けること」にあると思っています。
参加費もかかりますし「こんな小さいうちから発表会に出ても…」と考えて発表会に参加しないご家庭も正直多いのですが、発表会に行って、自分の子どもより1歳か2歳大きい子が円周率や詩を立派に暗唱・発表している姿は親にとっても大きな刺激となることは間違いありません。
我が家も年少前クラスで参加した発表会で親子ともども刺激を受け、暗唱に力を入れるようになりました!
4.息子の現状
4年間の七田式教育を通じ、「記憶力」と「自信(自己効力感)」を手に入れ、「練習することの大切さ」を知り、「粘り強さ」と「椅子に座って先生の話を聞き、取り組む力」が身につきました。
具体的には、3歳から暗唱を頑張るようになって、覚えることが得意になりました。併せて、覚えることに自信がついた様子が見て取れます。
また、暗唱の発表で間違えてしまった時やうまく覚えられない時に「悔しい」という気持ちを強く持つようになりました。悔し涙を流しながら家で練習をし、先生の前で成功した時には一回り成長したと感じました。
加えて、ほぼ毎週レッスン時に暗唱の発表をしている&発表会での発表を経て、あまり緊張せずに人前で発表することができます。
(見ている私は毎回緊張してしまいますが、本人は「緊張しない」と言っています。)
毎回50分間のレッスンを座って行っていますので、1時間程度は椅子に座っていられるようになっています。
5.七田式の悪影響
七田式と並行して公文の教室にも通い始めた頃、公文の先生から「七田式に通い始めて精神的に不安定になったという生徒さんがいたけど、お宅は大丈夫?そういう話を時々耳にするけど…」といったことを言われました。
そう言われてから気にかけていると、たまにそういった噂を耳にするのですが、「七田式教育が原因で精神的に不安定になる」ということは私には考えられません。
考えうるとしたら、「家庭でのフラッシュカード等の取り組みに親御さんが熱心になりすぎて強要してしまう」などでしょうか…。
通室している子ども達にそういった様子は見受けられませんし、むしろ、人の話をちゃんと聞ける、座ってレッスンを受けられる子ばかりです。
もちろん、親子ともに「七田式教育が合わない」ということはあると思いますが。
6.七田式は正直おすすめ?いつから?
これまで4年間息子が通った結果、七田式はおすすめだと言えます!
ただし、通うなら物心つく前から通室するのがおすすめ。
フラッシュカードや右脳での記憶力を最大限に活かせますし、3歳以降から通室する場合には、お子さんによっては「50分間座っていられない」「フラッシュカードに集中できない」という状況になる可能性があるためです。
また、せっかく通室するなら、発表会に参加して刺激を受けること、暗唱にチャレンジして子どもの能力を引き出すと、七田式教育の効果を最大に活かせると思います。
レッスンで使用する取り組み教材も良質なので、家庭での遊びに取り入れると更に良いと思います。
が、年齢が上がってくると他のおもちゃ(我が家ではプラレールなどなど…)が強豪になってきて、取り組み教材に興味を持たせるのはかなり努力が必要で、我が家では取り組み教材がなかなか使えていません。。
しかし、取り組み教材を予習しておくことで教室でスムーズに取り組めるようになり本人も自信がつくので、クラス(学年)が上がって新しい教材になったタイミングでは、少なくとも子どもがやり方をマスターするまでは家でも取り組んだほうが良いです。
上記の通り普段は取り組み教材を使えていない我が家ですが、年度初めにはレッスン前日などに練習させました。
プリントコースも良質で評判も良く、通室生でプリントコースを併用しているご家庭も多く見かけます。(オンラインショップなどでプリントだけでも購入可能です。)
我が家は公文もやっており七田式プリントに割く時間が作れないため七田式のプリントコースはやっていないのですが、通室生でプリントコースをやっている場合、一定量を達成すると名前・日付入りの記念トロフィーがもらえるようになっています!
このように基本的にかなりおすすめですが、ただ、どんなものでも「合う」「合わない」はあると思います。
兄弟・姉妹で通っているご家庭も多いですが、「上の子には合っていたけど下の子には合わなかった」というご家庭も見かけます。
まずは体験レッスンをしてみてもいいかもしれませんね!